訪問看護に興味はあるけれど、「子どもが小さいうちは難しいかな…」
「育休ってちゃんと取れるの?」と不安に感じていませんか?
実は、訪問看護は育児と両立しやすい働き方のひとつです。実際、私も息子が生まれた際に育児休暇を取得しました。
この記事では、訪問看護での育児休暇制度や実際の取りやすさ、復帰後の働き方についてわかりやすく解説します。
① 訪問看護でも育児休暇は取れるの?
結論から言うと、訪問看護でも産休・育休はきちんと取れます。
育児休業は「育児・介護休業法」に基づいた制度であり、事業所の規模に関係なく、一定の条件を満たせば利用可能です。
- 産前休暇:出産予定日の6週間前から
- 産後休暇:出産の翌日から8週間
- 育児休暇:子どもが1歳になるまで(最長2歳まで延長可)
正社員であればもちろん、条件を満たしたパート勤務でも取得できます。
ただし、小規模ステーションでは「代替スタッフの確保が難しい」という理由で、取得しにくいケースもあります。
② 育児休暇が取りやすい訪問看護ステーションの特徴
訪問看護ステーションによって、制度は同じでも**実際の“取りやすさ”**には差があります。
以下のような職場は、子育て看護師にとって働きやすい環境です。
- スタッフ数が多く、代行訪問の体制がある
→休暇中も他スタッフでカバーできる。 - 子育て世代のスタッフが多い
→「お互いさま」の文化がある。 - 時短勤務・午前のみ勤務などの柔軟なシフト制
→復帰後も無理なく働ける。 - リハ職・看護師のチーム連携がスムーズ
→負担の偏りが少ない。
🗣️ 現場の声:
「うちは半数がママ看護師なので、子どもの発熱にもすごく理解があります」
「育休明けは午前訪問だけで調整してもらえました」
③ 実際の流れ:産休・育休の手続きと給付金
育児休暇の申請方法は、病院勤務とほぼ同じです。
✅ 手続きの流れ
- 出産予定日の1〜2か月前に、管理者へ申請
- 産前産後休暇を取得(健康保険の「出産手当金」あり)
- 育児休暇へ移行(雇用保険の「育児休業給付金」あり)
- 復帰スケジュールを相談
育児休業給付金は、雇用保険に1年以上加入していることが条件です。
最初の6か月間は給与の67%、その後は50%が支給されます。
🗣️ ポイント:
小規模ステーションでも、雇用保険・健康保険加入があれば同じ給付を受けられます。
手続きは職場が代行してくれることが多いので、早めに相談しましょう。
④ 育休明けも安心!訪問看護の柔軟な働き方
訪問看護は、家庭と両立しやすい職場環境が整っているケースが多いです。
- 夜勤がない
- シフトの自由度が高い(週3日、午前のみなど)
- 直行直帰OKの職場もある
特に子どもが小さい時期は、時短勤務や1日3件程度の訪問など、負担を調整できる働き方を選ぶ看護師も多くいます。
🗣️ 実際の声:
「子どもを保育園に送ってから9時半出勤、15時半には退勤。病棟よりずっと楽になりました。」
「直行直帰できるから、通勤時間が減って家事の時間が増えた。」
⑤ 育休・時短勤務で気をつけたいポイント
- 職場の方針を確認する
→育休中の社会保険・給付金の取り扱いをチェック。 - 早めに上司と復帰プランを共有する
→復帰後の勤務日数や担当件数をすり合わせておく。 - 同僚との連携を大切に
→代行訪問への感謝を言葉で伝えると、復帰後の関係も良好に。
⑥ まとめ:訪問看護は“育児と仕事の両立”がしやすい職場
訪問看護は、
- 夜勤がなく、
- シフトの調整がしやすく、
- 子育てに理解のある職場が多い。
つまり、育児をしながら長く続けられる働き方なのです。
「子どもが小さいうちは無理かも…」と感じる方こそ、
訪問看護の柔軟な働き方を一度検討してみてください🌿

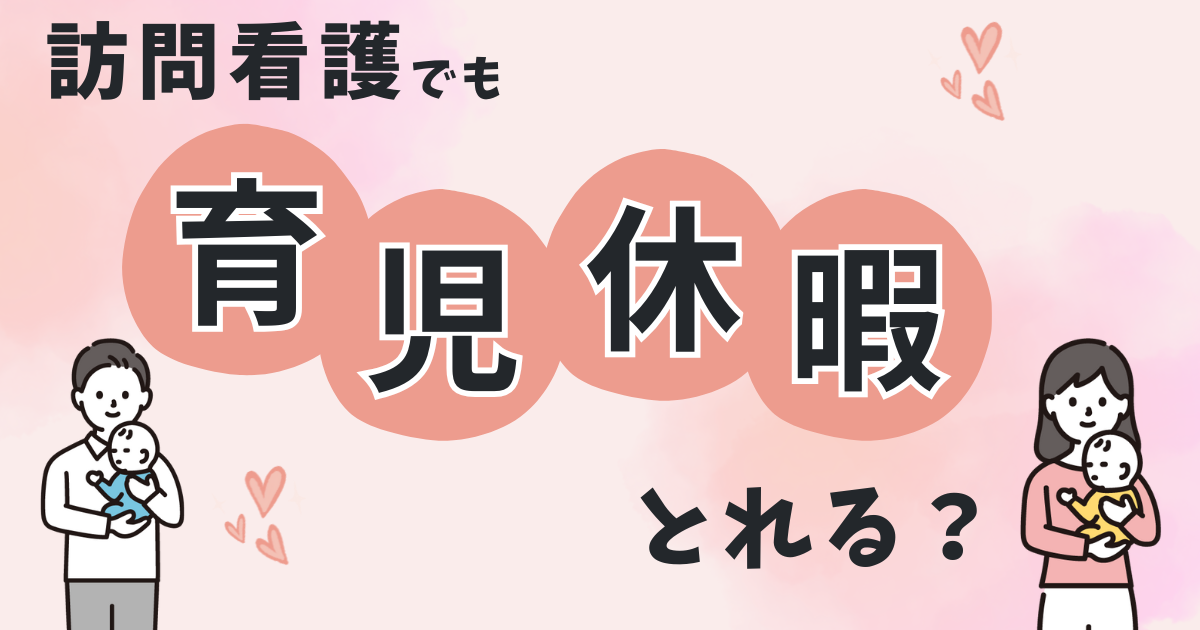
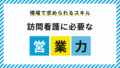
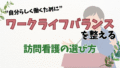
コメント