訪問看護に必要な「営業力」とは?現場で求められる本当のスキルを解説
訪問看護と聞くと、「看護のスキル」が一番大事だと思う人が多いでしょう。
しかし実際に働いてみると、「営業力」もとても重要だと感じる場面が多くあります。
「営業って苦手…」「看護師なのに営業するの?」
そんな不安を持つ方に向けて、今回は訪問看護で求められる“営業力”の本当の意味を、現場目線でわかりやすく解説します。
① 訪問看護に「営業力」が必要と言われる理由
病棟では、患者さんは病院に来てくれます。
でも訪問看護は、自分たちから“地域の中に出て行く”仕事です。
つまり「どんな人が利用してくれるか」は、自分たちの働きかけ次第でもあります。
訪問看護では、医師やケアマネジャー、地域包括支援センターなど、多職種との連携が欠かせません。
彼らから「このステーションなら安心してお願いできる」と思ってもらうことが、継続的な依頼や紹介につながります。
また、利用者や家族と信頼関係を築くことも非常に大切。
その積み重ねが“営業力”として評価され、結果的にステーションの安定した運営にもつながるのです。
② 「営業力」と聞いて構える必要はない
「営業」と聞くと、ノルマや契約を思い浮かべて苦手意識を持つ方も多いかもしれません。
でも、訪問看護で必要な営業力は**「売り込む力」ではなく「信頼を築く力」**です。
・笑顔であいさつする
・電話やメールに丁寧に対応する
・約束を守る、報告を欠かさない
こうした基本的な対応が、地域での信頼を生み出します。
つまり、“誠実なコミュニケーション”こそが訪問看護における営業力です。
③ 訪問看護師に求められる営業力の具体例
では、実際にどんな場面で営業力が発揮されているのか、具体的に見ていきましょう。
1. 初回訪問時の印象づくり
第一印象はとても大切です。
清潔感のある身だしなみ、落ち着いた声のトーン、穏やかな笑顔。
たった1回の訪問でも「この人になら安心して任せられる」と思ってもらえることが信頼づくりの第一歩です。
2. ケアマネ・医師との信頼関係づくり
ケアマネや主治医からの紹介が多いのが訪問看護の特徴。
報告・連絡・相談をこまめに行うことで、「このステーションは安心」と感じてもらえます。
電話1本、報告書1枚にも“営業力”が表れます。
3. 利用者・家族との関係性の維持
利用者さんの体調や家庭の事情は日々変化します。
その中で「いつも気にかけてくれている」「相談しやすい」と感じてもらうことが、継続利用につながります。
4. 地域での発信・連携
地域の勉強会やサービス担当者会議に参加し、顔を覚えてもらうことも大切です。
自分たちの強みを自然に伝えることで、少しずつ信頼の輪が広がっていきます。
④ 管理者・リーダーに求められる営業力
管理者やリーダーになると、より「地域とのつながり」を意識した営業力が求められます。
- ケアマネ事業所への定期訪問や電話での情報交換
- 地域連携会議への参加
- クレーム対応などでの誠実な姿勢
- スタッフ教育を通じた印象づくり
一人の対応がステーション全体の印象を決めることもあります。
地域から「このステーションは感じがいい」と思われるような関係づくりが、安定した依頼につながります。
⑤ 「営業が苦手…」という看護師へ
営業力と聞いて苦手意識を持つ人は多いですが、実は看護師として働く中で、すでに多くの人が“営業”をしています。
たとえば、
・患者さんや家族に信頼されるために努力する
・医師に分かりやすく報告する
・同僚と良いチーム関係を築く
これらはすべて、信頼関係をつくるという点で“営業力”と同じ要素を持っています。
訪問看護で必要なのは、「自分を信じてもらう力」と「相手の想いを受け取る力」。
その積み重ねが自然とステーション全体の営業力を高めていきます。
⑥ まとめ:訪問看護の営業力は「信頼づくりの力」
訪問看護における営業力とは、
“人との信頼関係を築く力”です。
それは、特別なスキルではなく、日々の丁寧な対応や思いやりの中にあります。
利用者・家族・多職種との信頼を積み重ねることで、あなた自身もステーションも成長していきます。
つまり、今日の「おはようございます」から、営業はすでに始まっているのです。
💡営業力を高める3つのコツ(まとめ)
- 「報・連・相」をこまめに行う
→小さな報告が大きな信頼につながる。 - “伝える”より“聴く”を意識する
→相手の立場を理解することで関係が深まる。 - 誠実な対応を続ける
→どんなときも丁寧に、まじめに。継続が力になります。
訪問看護の営業力とは、決して派手なスキルではありません。
それは「人としての信頼を積み重ねる力」。
看護師としてのやさしさと誠実さこそが、最大の営業力なのです。

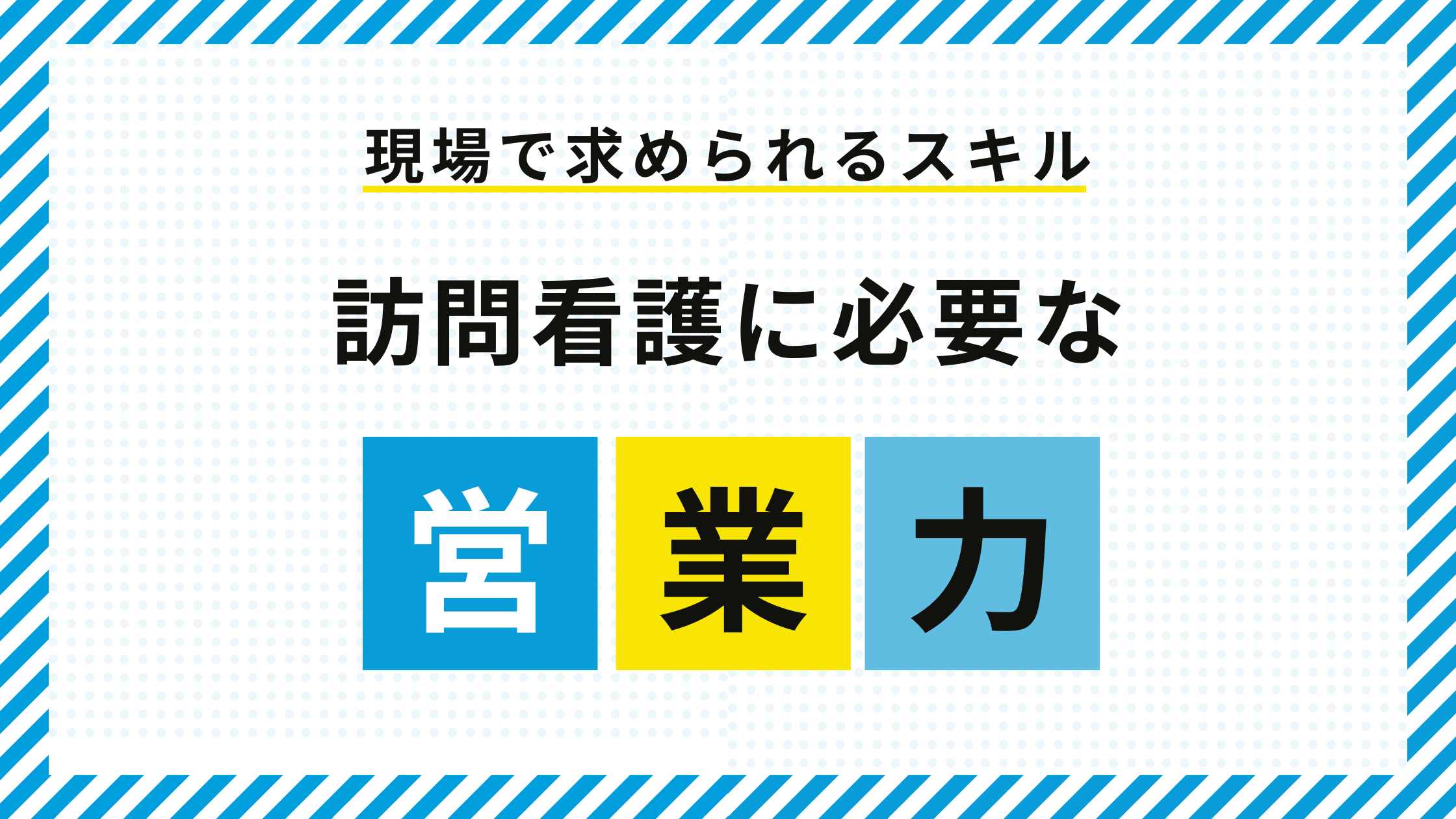

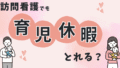
コメント